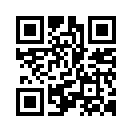2006年04月26日
実

実がなっている。黄色く色付き始めている。
下を通った子供が、まだ緑の実を見つけて、何で一つだけ違うの。と年上の友達に尋ねた。
聞かれた年上の友達は、きっと仲間外れにされているのだよ。と答えた。
かわいそうだね。何で仲間はずれにするのだろうね。と聞き返した。
年上の友達は何も答えなかった。
その夜雨が降り、風が吹き荒れました。
二人は次の日の朝、実が心配で見に行く事にしました。
木の下には、たくさんの実が落ちていました。
上を見ると、まだ緑の実は落ちないで昨日のままでした。
すると年下の子供が、やったやった、いじめに勝ったのだ。と言った。
年上の友達は微笑みながら、強くなろうね、と一言言った。
Posted by zinzin at
11:24
│Comments(0)
2006年04月25日
花


花が咲いている。右にも左にも、ここは花摘み園芸店。
皆、綺麗々と言われて摘まれていく。
私だって綺麗に咲いているのに、ただ葉っぱに小さな穴が一つあるだけなのに、誰も摘んでくれない。
その時、一人のお婆さんが私を見つけて、これに決めたと言ってくれた。
嬉しかった。
お婆さんの為に何時までも綺麗に咲いてやるぞ。
小さな穴だって虫さんも私が一番元気だと知っていたから来たのだ。
うわべばかり見てもダメなのだ。もっとしっかり見なければ、人間だって同じだよ、良いところを探さなければいけないのだ。
Posted by zinzin at
11:14
│Comments(0)
2006年04月24日
襖
山村の一番奥にある屋敷は明治に建てられた萱葺屋根の大家であった。
以前は老夫婦が住んでいて二十三年前迄は林間学校に使用されていたが、ひとつの出来事を期に利用される事が無くなった。
今は面影も無い。湖水に沈んでいるが、渇水の時屋根を垣間見る事が出来る。
この話は昭和二十九年夏の日の出来事である。
「ミーンミンミン、ミーンミンミン」早朝から毎日聞こえる。
村人なら気に掛ける事も無かろうが、都会から来たものにとっては、始めは情緒だなんていっているが日を数えるうちに騒音になる。
子供たちは気に掛けるものはいないが、付き添いの人には苦痛そのものだ。
東京中野から四年の児童十三人、女子先生三人、群馬水上にある大家に来て四日目の事である。
裏山で写生し帰った時は全員いたはずだが、夕餉の時一人いない。
丸山キミの姿が見えない。
裏山も、涼をとった河原も探した。山郷の夕暮れは早い、村中の人が提灯を下げて探した。
見つからない、まだ十歳も女の子が何処へ行くのか想像もつかない。
夜通し探した。あらゆるところを探した。
神隠しに遭ったと村人は言う。
中野から丸山キミの両親と叔母が水上に着いたのはキミが不明になった次の日の十一時過ぎであった。
叔母は祈祷師を呼んで捜したほうが良いと言って効かないので、隣村から七十過ぎの屑目祈祷師を呼ぶことにした。
祈祷師は庭の大きな杉の木に向かって祈る事四十五分、突然声が変わった。
裏の古井戸、裏の古井戸と何度も繰りかえした。
家の老夫婦は、二年前からこの家を管理しているが古井戸などないと言うが、叔母は聞く耳をもたない。
そこで村人に頼んで家の裏を探してもらう事にした。
村人は生い茂った雑草を鎌で切り払いながら古井戸を探した。
雑草はシダ類と小木に巻きついた蔓が多く敷地内といっても里山そのものであった。
「アッタゾー」と声が聞こえたのは午後四時丁度の事であった。
キミの両親も、叔母も、付き添えの先生も、生徒も、村人も全員草の刈り取られた家の裏に集まった。
オニゼンマイの根が覆い被さっていたが、古井戸に間違いない。
叔母は穴に向かって「キミ-、キミ-」と大きな声で叫んだ。
声は木霊となり、遠くの山から「キミ-、キミ-]と帰ってきた。
村人が二人で古井戸を覆っていたオニゼンマイの根を力任せに手前に引いた。勢い余って二人は根をもったまま後ろに倒れた。
「クスクス」児童の一人が笑った。又一人、又一人、笑いの渦となり消えていった。
町の駐在所から来た巡査が笑うのじゃない。皆が心配している時にと言いながら児童を睨みつけた。
巡査は「手帳を見ながら、この家では二年前と四年前にも児童が行方不明になって未だに解決していない。これはどう言う事なのだ。何か聞いていないかね」と老夫婦に尋ねた。
老夫婦は困った顔をしながら「私たちは何も聞いていません」と答えた。
「まだ解決してなかったのかね」村人は巡査に尋ねた。
今度は巡査が困った顔をして大きな咳払いをして、その件に関しては本署のほうで行っているので良くわからない。と言って言葉を濁した。
巡査は懐中電灯で古井戸の中を確かめながら「何も無いようだね」と言った。
皆は大家の縁側で二年前と四年前の出来事を巡査から聞く事にした。
巡査は古い手帳を見ながら「この村での事件はここ十年で二件より起きていない、この事件を入れて三件だけだ」と眼鏡に手帳を近づけていった。
「二年前も四年前も今度と同じ八月二日だ」巡査は確認するかのように頭を縦に軽く振りながらボソボソと言った。
「二人は十歳と同じ歳だが、今回いなくなった丸山キミさんは」巡査は尋ねた。
「昭和十二年八月二日生まれで十歳いや、十一歳になったところです」母の丸山シゲが答えた。
「一歳違うか」巡査がタバコの灰を人差し指で叩きながら言った。
一同は黙って巡査の言う事を聞いた。
巡査の目が鋭くなった。
「前の二人も同じ八月二日生まれ、と言う事は十歳でなく十一歳」難しい顔で巡査が言った。
「本署で二人の歳を調べなおし必要がある」と言い自転車に乗ろうとした時「キミちゃんいるよ」と言いながら奥のほうから寺岡ノブ走ってきた。
全員の視線が寺岡ノブに向けられた。
「何処何処」叔母が寺岡ノブの両腕をつかみながら聞いた。
ノブは一番奥の十二畳の部屋に皆の先に立ち入った。そして襖を指差して「ココ、ココ」と言った。
襖は普通の倍の大きさで二枚あり、襖絵は二枚で一枚の絵になっていた。
だいぶ古い襖絵だが御宮とそこで遊ぶ子供が描かれていた。
「カゴメ、カゴメ、かごの中の」歌声が聞こえた気がした。確かに聞こえた。
真新しい着物を着た少女がいた。
丸山キミだ。「キミ-、キミ-]と叔母が大きな声で呼んだ。
襖の中の少女は楽しそうに遊んでいる。右側の少女も、その右の少女も。
もうこの話を口にする人は誰もいない。ただ。湖水から大家の屋根が見えた時「カゴメ、カゴメ」の歌声が今でも聞こえるとの事である。
Posted by zinzin at
11:39
│Comments(0)